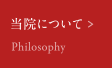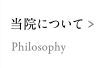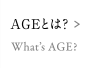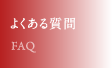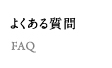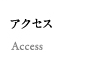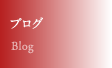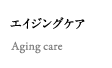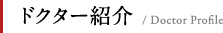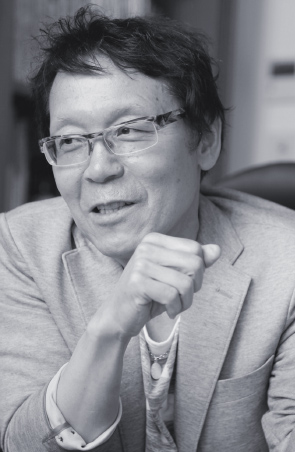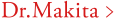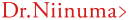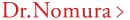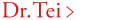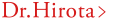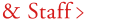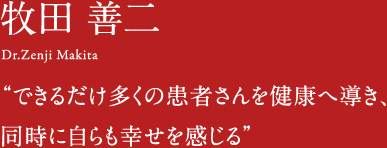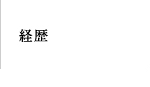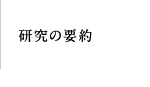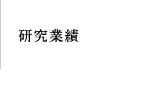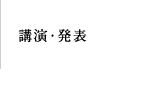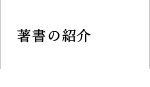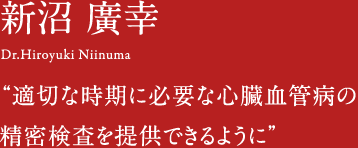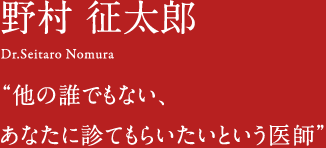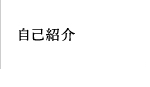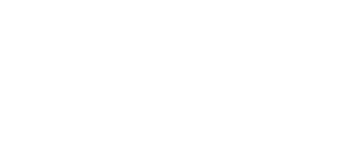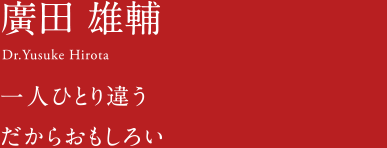| 種別 |
タイトル・掲載の詳細 |
| 原著 |
65) Yamagishi S, Amano S, Inagaki Y, Okamoto T, Koga K, Sasaki N, Yamamoto H, Takeuchi M, Makita Z: Advanced Glycation End Products-Induced Apoptosis and Overexpression of Vascular Endothelial Growth Factor in Bovine Retinal Pericytes. Biochem Biophysical Res Commun 290:973-978, 2002 |
| 総説 |
54) 古賀康八郎、山岸昌一、牧田善二:糖尿病の非薬物療法の基本. 大道学館出版部 臨床と研究 79:35-37, 2002 |
| 著書 |
32) |
| 原著 |
66) Okamoto T, Tanaka S, Stan AC, Koike T, Kase M, Makita Z, Sawa H, Nagashima K.
Advanced glycation end products induce angiogenesis in vivo.
Microvasc Res. 2002 Mar;63(2):186-95. |
| 原著 |
67) Yamagishi S, Inagaki Y, Okamoto T, Amano S, Koga K, Takeuchi M, Makita Z.
Advanced glycation end product-induced apoptosis and overexpression of vascular endothelial growth factor and monocyte chemoattractant protein-1 in human-cultured mesangial cells.
J Biol Chem. 2002 Jun 7;277(23):20309-15. |
| 原著 |
68) Sasaki N, Takeuchi M, Chowei H, Kikuchi S, Hayashi Y, Nakano N, Ikeda H, Yamagishi S, Kitamoto T, Saito T, Makita Z.
Advanced glycation end products (AGE) and their receptor (RAGE) in the brain of patients with Creutzfeldt-Jakob disease with prion plaques.
Neurosci Lett. 2002 Jun 28;326(2):117-20. |
| 原著 |
69) Schwab W, Friess U, Hempel U, Schulze E, Makita Z, Kasper M, Simank HG.
Immunohistochemical demonstration of -(carboxymethyl)lysine protein adducts in normal and osteoarthritic cartilage.
Histochem Cell Biol. 2002 Jun;117(6):541-6. |
| 原著 |
70) Yamagishi S, Okamoto T, Amano S, Inagaki Y, Koga K, Koga M, Choei H, Sasaki N, Kikuchi S, Takeuchi M, Makita Z.
Palmitate-induced apoptosis of microvascular endothelial cells and pericytes.
Mol Med. 2002 Apr;8(4):179-84. |
| 原著 |
71) Miyoshi H, Taguchi T, Sugiura M, Takeuchi M, Yanagisawa K, Watanabe Y, Miwa I, Makita Z, Koike T.
Aminoguanidine pyridoxal adduct is superior to aminoguanidine for preventing diabetic nephropathy in mice.
Horm Metab Res. 2002 Jul;34(7):371-7. |
| 原著 |
72) Yamagishi S, Inagaki Y, Amano S, Okamoto T, Takeuchi M, Makita Z.
Pigment epithelium-derived factor protects cultured retinal pericytes from advanced glycation end product-induced injury through its antioxidative properties.
Biochem Biophys Res Commun. 2002 Aug 30;296(4):877-82. |
| 原著 |
73) Kikuchi S, Shinpo K, Ogata A, Tsuji S, Takeuchi M, Makita Z, Tashiro K.
Detection of N epsilon-(carboxymethyl)lysine (CML) and non-CML advanced glycation end-products in the anterior horn of amyotrophic lateral sclerosis spinal cord.
Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord. 2002 Jun;3(2):63-8. |
| 原著 |
74) Inagaki Y, Yamagishi S, Amano S, Okamoto T, Koga K, Makita Z.
Interferon-gamma-induced apoptosis and activation of THP-1 macrophages.
Life Sci. 2002 Oct 11;71(21):2499-508. |
| 原著 |
75) Okamoto T, Yamagishi S, Inagaki Y, Amano S, Koga K, Abe R, Takeuchi M, Ohno S, Yoshimura A, Makita Z.
Angiogenesis induced by advanced glycation end products and its prevention by cerivastatin.
FASEB J. 2002 Dec;16(14):1928-30. |
| 原著 |
76) Atsumi T, Chesney J, Metz C, Leng L, Donnelly S, Makita Z, Mitchell R, Bucala R.
High expression of inducible 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase (iPFK-2; PFKFB3) in human cancers.
Cancer Res. 2002 Oct 15;62(20):5881-7. |
| 原著 |
77) Takeuchi M, Yamagishi S, Makita Z.
[OPB-9195]
Nippon Rinsho. 2002 Sep;60 Suppl 9:606-10. Review. Japanese. No abstract available. |
| 原著 |
78) Petrova R, Yamamoto Y, Muraki K, Yonekura H, Sakurai S, Watanabe T, Li H, Takeuchi M, Makita Z, Kato I, Takasawa S, Okamoto H, Imaizumi Y, Yamamoto H.
Advanced glycation endproduct-induced calcium handling impairment in mouse cardiac myocytes.
J Mol Cell Cardiol. 2002 Oct;34(10):1425-31. |
| 原著 |
79) Koga K, Yamagishi S, Okamoto T, Inagaki Y, Amano S, Takeuchi M, Makita Z.
Serum levels of glucose-derived advanced glycation end products are associated with the severity of diabetic retinopathy in type 2 diabetic patients without renal dysfunction.
Int J Clin Pharmacol Res. 2002;22(1):13-7. |
| 原著 |
80) Yamagishi S, Amano S, Inagaki Y, Okamoto T, Takeuchi M, Makita Z.
Beraprost sodium, a prostaglandin i2 analogue, protects against advanced gycation end products-induced injury in cultured retinal pericytes.
Mol Med. 2002 Sep;8(9):546-50. |
| 原著 |
81) Koga K, Yamagishi S, Takeuchi M, Inagaki Y, Amano S, Okamoto T, Saga T, Makita Z, Yoshizuka M.
CS-886, a New Angiotensin II Type 1 Receptor Antagonist, Ameliorates Glomerular Anionic Site Loss and Prevents Progression of Diabetic Nephropathy in Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty Rats.
Mol Med. 2002 Oct;8(10):591-9. |
| 原著 |
82) Schwab W, Friess U, Hempel U, Schulze E, Makita Z, Kasper M, Simank HG.
Immunohistochemical demonstration of -(carboxymethyl)lysine protein adducts in normal and osteoarthritic cartilage.
Histochem Cell Biol. 2002 Jun;117(6):541-6. Epub 2002 May 22. |